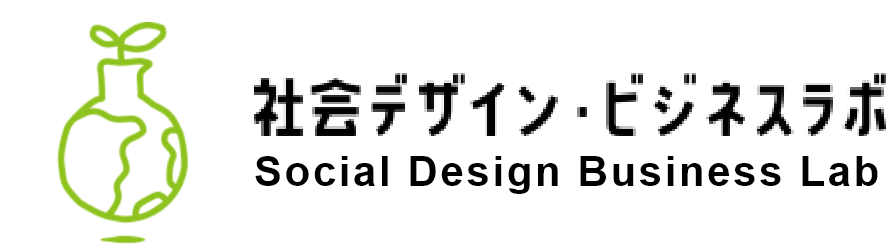コンテンツ
CONTENTS
コンテンツ詳細
ブルーブラックマガジンより
社会デザインの物語
~関係性の編み直し編~

一般社団法人 社会デザイン・ビジネスラボの代表理事である中村 陽一氏が連載中のウェブマガジン「ブルーブラックマガジン」(運営:株式会社ブルーブラックカンパニー)へ、9月2日に開催された社会デザイン・ビジネスラボオープニングイベントについての記事が掲載されておりますのでご紹介いたします。
ブルーブラックマガジンはこちら
社会デザイン・ビジネスラボとは?
2022年9月2日は社会デザイン・ビジネスラボ(以下、SDBL)にとって節目の日となった。
SDBLとは、株式会社JSOLと立教大学社会デザイン研究所との連携協定をもとに、2019年12月に立ち上げられた場で、社会課題への真剣な取り組みから新たなビジネスの機会を生み出し、持続可能な社会とそこでのビジネスを検討するためのプラットフォームとして、防災、地方創生、教育などさまざまなテーマでワークショップやプロジェクトを進めてきた。22年4月からは自立した場としての活動となり、6月には一般社団法人となった。
設立の狙いは、1)社会課題解決と事業創造における新しい関係性の構築、2)社会デザインの発想によるソーシャルビジネスの推進、3)社会的な価値を生む人財の育成で、その実現のため、①ワークショップ事業、②ソーシャルビジネス推進事業、③社会デザイン研究・教育事業を行っていく。
代表理事を務める私の思いとしては、社会デザインの発想と方法論をビジネスの世界のど真ん中に持ち込むことによって、ビジネスを「本来の(ありうべき)姿」に立ち戻らせたいという大それた(?)「野望」がある。実におこがましいミッションステートメントであることは承知のうえで、しかしこのくらいのことを掲げないと、21.5世紀の日本の姿は描けないのでは? という危機意識もあってのことである。
今回は、9月2日のオープニングイベント「社会課題解決と事業創造キックオフ」の会場で繰り広げられた関係性のストーリーにスポットを当てて行きたい。
オープニングイベントの場で繰り広げられた語りと対話
会場となったLIFORK原宿は、越境型・創発型のやり取りを交わすにふさわしい開放的な空間デザインが用意されており、参加された方たちも、おそらく何らかのワクワク感を感じながら開始を待つことができたのではないかと思う。
当日の流れは以下のようなものだった。全体のモデレーターは、SDBL理事でもある谷本有香さん(Forbes JAPAN 執行役員 Web編集長)に務めていただいたが、途中非常に的確なコメントをはさみながらの進行により、限られた時間でありながら深くもある時間の流れを共有できたことをまず特記しておきたい。
私が開会挨拶でSDBLに込めた思いを語った後、三尾幸司事務局長(株式会社JSOL ビジネス・デザイン&マーケティング部長)によるSDBLの概要説明があり、第一部のメディア公開セッションでは、木村智行さん(株式会社日本総合研究所 創発戦略センター マネジャー)、西秀記さん(青森商工会議所 副会頭/SDBL理事)、石井綾さん(一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワーク 執行役員)に、それぞれ取り組んでこられた事業や活動を通じてのSDBLとの接点を語っていただいた。
続いて、第二部のSDBL理事によるパネルディスカッションには、冨田昇太郎さん(ホクセイ・プロダクツ株式会社 代表取締役)、原ゆかりさん(株式会社SKYAH 代表取締役)、福井崇人さん(クリエイティブ・ディレクター)、安渕聖司さん(アクサホールディングス・ジャパン株式会社 代表取締役兼CEO)が登場。
「社会課題解決で最も大事だと思うこと(+事例)と、SDBLを活用した未来」について、会場とオンラインとのやり取りとは思えないインタラクティブな対話が熱く展開され、増田裕一さん(株式会社JSOL 常務執行役員/SDBL理事)の期待を込めた閉会挨拶で締めくくられた。
越境型の多層多重な多様性が交差する地点の物語
2時間ほどの当日のセッションおよびパネルには、社会デザインとビジネスをめぐって今起こっている「物語」が、象徴的に凝縮されていたように思う。
まず、当日のスピーカーはもとより、参加者の何重かの意味における多様性に注目したい。企業において日々ビジネスの現場にいる人たち、サードセクターで社会性と密接につながった活動を続けている人たち、メディアで公共性と関わりつつ仕事を進めている人たち等々の多様性はいうまでもなく、実はここに集まった人たちの多くは単純にそれぞれのセクターだけで生きている人たちではない。つまり、個人のうちにも何らかの多様性・多重性をもつ人たちだった。
たとえば、原ゆかりさんのように、外務省→〝NGOと並行して総合商社〟→〝NGOの運営者であると同時にソーシャルビジネスの経営者〟といった軌跡が決して珍しくないほど、いわゆるパラレルキャリアや副業・複業、プロボノの世界を自然に生きている参加者が多く、しかも皆、志と力は持っていても、スーパーウーマンやスーパーマンではない。事の大小はあっても、失敗や挫折を経験している人も多いのである。
思えば、過去にも「異業種交流」と呼ばれる場はあった。私も幾度も立ち会ったことがあるが、そこに横溢する「何かビジネス(儲け話)の役に立つ情報はないか」「自分をアピールする機会があるのではないか」「有力なコネクションにつながれないか」といったギラギラ感に、居心地の悪さを感じることの方が多かったように思う。いや、そうした野心を持つこと自体は否定しないのだが、皆、どこか不慣れでぎこちなかったところに違和感があったのかもしれない。
いまやそうしたぎこちなさはほとんどない。ここに集まった人たちだけが特別なわけではなく、そういうふうに、社会性と公共性と事業性と、さらには越境型の関係性を同時に生きる生き方・働き方のストーリーが一般化し始めていることは見逃せないと思う。
むろん、まだそうした生き方が多数派になっているとは言えない。この社会には、そのような働き方・生き方など、遠い世界の絵空事に映る「現実」を生きている人たちの方がおそらくはまだ多いし、それを「自己責任」の一言で片づけることなど誰にもできはしない。
しかし、それでもなお、ここで進行している物語に私は隔世の感を覚える。私がいま取り組んでいるようなことをおぼろげに考え始めた40年ほど前には、おそらく9月2日のこの場で語られたようなことは、世間知らずの物言いとみられたであろうし、社会に適合できない変人の戯言か、逆に社会を超越した存在の突飛な発言ないし綺麗事で片付けられたことだろう。
いずれにせよ、とてもまともな考えとは見られなかったのである。
少なくとも、社会の「常識」の一部はその程度のもので、いくら硬い岩盤のように見えても、それは変わりうるのだということだろう。実際、この国、この社会の何十年かを見ていると、案外、あっさり分水嶺やティッピングポイント(転換点)を超えてしまった例は少なくない(好ましいケースばかりではないし、社会ががらりと変わるわけでもなく、いわば前近代と近代とポスト近代が同時に存在はするのだが)。
また、最初からこの時代を生きる若い世代が、それを心地よいと感じるか、むしろ社会の変容がもたらした多様性を重荷に感じるか、さらには先行世代に向けるまなざしがより厳しいものになっていくのかどうか、そこにおける新たな分水嶺にも、これからの社会デザインは目を向けて行くことが大切になってくると私的には感じている。
いいかえれば、歴史の時系列的な縦軸とイシューによる横軸が交差する地点のデザインに、どのように共に参加できるかということかもしれないと、私にとっては明らかに交差する地点そのものといえるこの日この場所で、あらためて思い至ったのだった。
いずれにしても、当日交わされた対話に、越境型の多層多重な多様性の拡大をあらためて実感できたのは大きな収穫であった。
【いしはらこはるさんによるグラフィックレコーディング】


外連とリアル―プラスチックワードに堕すことなく
当日語られたキーワード―サステナビリティ、パーパス(経営)、ESG投資、コアバリュー、ウェルビーイング、さらには、アンコンシャスバイアス、マイクロステップetc.―いつもながらカタカナ文字が多くて舌を噛みそうだねと揶揄されそうだが、これらの背景にある地域や事業現場の現実は、決して空中を浮遊したり、内実のない空洞だったりするものではない。
ここで起こっている社会デザインの「物語」の2つめの論点と思えるのが、本稿のリードでもふれた「外連という方法をとりつつ、社会課題の現場のリアルと向き合い続ける『(事業)運動戦略』の場で紡がれる関係性の物語」である。
上記したキーワードはいま、何となく耳ざわりのよいキャッチコピーとして、巷にあふれ始めている。そういう使い方が得意な業界の人達も多く存在する。まさにプラスチックワード(何となく何かを言っているように見えるため、多くの人が使ったりするが、その実何も言っていないに等しい空疎な言葉)に堕していく可能性も持った諸刃の剣となりうるワード群である。
ただ、それだけでこうしたワード群が登場しているわけではないことにも目を遣る必要がある。大事なのは、こうしたワードが表している社会的な課題の現実と向き合うデザインといえる。もしそうした現実と向き合うことを諦めたり、やめたりすれば、プラスチックワード化は避けられない。
思えば、私が創設から20年間在籍した社会人大学院(立教大学21世紀社会デザイン研究科)でも、さまざまなある種流行りのキーワードのリアルからできうる限り逃げずに社会課題の現場と向き合っていこうとしてきたことによって、何とかプラスチックワード化を免れてきたかなという感がある。その辺りぎりぎりの線をいく戦略に特徴があったのではとも思う(それは私の方法だったかもしれないが…)。リスクも少なくないやり方ではあったが、それが「得体の知れない」面白みにもなっていたはずである。
そういう一種の「外連味」には、学界でもたえず「学問ではない」と異端視され続けてきた「歴史」もあって、結構隠れた自負があるというと自虐が過ぎるかもしれないが、いわば、プラスチックワードとみえる外連味で耳目を引きつつ、社会変革の現場のリアルへとつないで行こうとする「運動戦略」だった。歌舞伎や文楽において、観客を楽しませるために用いられる演出(早替わり、宙乗り、大道具小道具の仕掛けなど)としての「外連」を思い起こしていただければ幸いである。
評価は後世を待たねばわからないが、そうでなければ、少なくとも面白い人たちが数多く集ってくる可能性は拓けなかった気がするのだ(もちろん、それを支えたり、裏付けたりする場とスタッフとプログラム等の充実が大前提だが)。
SDBLの法人化の節目で交わされた議論を反芻しながら、この辺りこそ、さまざまな価値観を持つ人びとと、ぜひ自由な対話を重ねた先に、さらに新たな社会デザインの物語を紡ぎ出せたらと夢想した半日でもあった。